
どーも!グッチー@098takashiです。
先日浦添市の天然海岸「カーミージー」を散策しました。
子どもが海の生き物観察が好きなので、よく訪れています。
近年はトイレや駐車場が整備され、子ども連れには大変行きやすい海岸となりました。
都市型のビーチとしては珍しく天然海岸が残っていて、多様な生き物を観察することができます。
過去にはタコとか細長いヨウジウオとか観察することができました。
そんなカーミージーで、今回はなんと「ハリセンボン」と遭遇しました。
カーミージーに関心のある方は必見です。
浦添市天然海岸「カーミージー」

浦添市の天然海岸カーミージーは下記のブログに詳しく紹介しているのでご覧ください。
カーミージーを大きくわけると、宜野湾北谷方面を望み「里浜」と呼ばれる天然海岸側と、遠浅が広がるパルコシティ側の海があります。
今回は天然海岸側を散策しました。

ただ残念なことに、2025年4月現在では天然海岸の半分が浦添西海岸道路の建設のため、フェンスが建てられてしまいました。
市民の憩いの海岸なので、早く全面的な利用再開をしてほしいものです。
カーミージーの里浜

カーミージーの良いところは、自然の海岸の景観が残っているとこです。
那覇から浦添、宜野湾にかけて、港湾整備されているので埋立整備された海岸線がずっと続いています。
そんななかでも、カーミージーは自然海岸と砂浜、浅瀬が広がっている良きビーチなんです。

カーミー自体は「亀瀬御嶽」がある場所でもあります。
御嶽は関係者以外立ち入り禁止となっています。
普通にみんなあがっていきますが、モラルをもって海岸散策したいですね。

天然の海岸なので、波に浸食された海岸の景観が見ものであります。
すごいですよね。
長時間かけてこんな奥深くまで浸食していくのですから。
でもこのおかげでこの岩の下が一日中日陰になるものですから、テントもいらず休憩場所を確保できます。

こちら浦添西海岸道路の向こう側は、いつも比較的に人が少なく落ち着いて過ごすことができる場所であります。
こんな感じでトンネルのような場所もあったりして。

子どもたちにとっては探検気分で面白いでしょうねえ。

そしてこちら側の海岸を散策しているときになんと得体のしれない物体が砂浜に打ち上げられていたのです!!
カーミージーにハリセンボンが!!

なんとなんと、散策していたら砂浜にハリセンボンが打ちあがっていました!!
子どもも目の前で初めて見るハリセンボンに大興奮!
死んでしまっていると思いきや、網にいれると怒って膨らんてきました!!

カーミージーは天然海岸なので、あちこち潮だまりがあるんですね。
とりあえずその潮だまりに入れてみてしばらく観察。
すると見事にスルスルと怒った風船がしぼんでいきました。

元気そうだったので、また海に戻してあげました。
もう二度と打ち上げられるんではないぞ、ハリセンボンボン!!
この日見つけたおもろ生き物は「シャコ」

シャコは見つけるとすぐに穴に引っ込んでしまうので、捕まえることができて息子も大喜びでした。
やはりフェイスが特徴的なので、観察しがいがあります。
そのほかにもヒトデやウニ、貝などたくさんの生き物を見つけることができるので、注意深く潮だまりや穴を見てみましょう。
私より詳しい生き物博士の息子と歩いていると、あれこれ見つけて説明してくれるので面白いです。
今日のエンジョイ!

カーミージー散歩
今回は海の中の映像や画像はありませんが、海の中に潜ってみるとサンゴや生き物が本当に多様に観察することができます。
現在浦添西海岸道路の工事中で半分は遊べないようなフェンスが建てられています。
これが将来撤去されて元のカーミージーに戻るのがいつなのかはまだわかりません。
カーミージーは最近人気があって、週末に訪れるとテントを建ててBBQをやっている方などもいらっしゃいます。
人によっては釣りをしているし、散策しているし、潜っているしで、大勢でにぎわうこともあるカーミージーです。
駐車場が整備され、足洗い場もあることから、幼児連れのかたでも訪れやすいと思います。
ただし、クラゲネットが設置されていない天然のビーチですので、海での遊泳は細心の注意が必要です。
実際に近くの港川の川でカツオノエボシをみかけてことがあります。
引き潮の時に浅瀬を散策する場合には、シャコなども触るのは危険です。
シャコに「バチっ」と叩かれたら、激痛の激痛です。
生き物観察は楽しいです。
ですが、海の生き物は危険でもあります。
カーミージーでは猛毒を持つ「イモガイ」も見かけたことがあります。
多様な生物が生息しているからこそ、自然に対して敬意をもって楽しみたいと考えています。
また今年も夏がやってきます。
リゾートビーチにはない、多様な生き物を観察できる
「カーミージー」
ぜひ、機会があれば訪れてみてください。
それではまた!


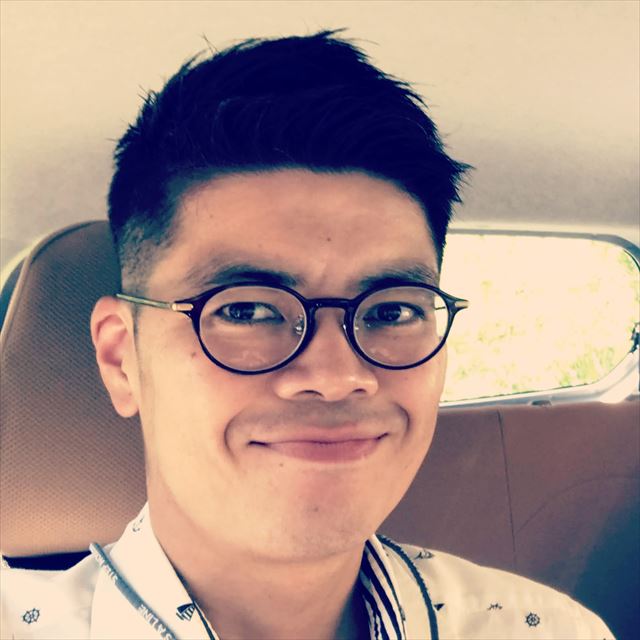


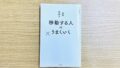
コメント